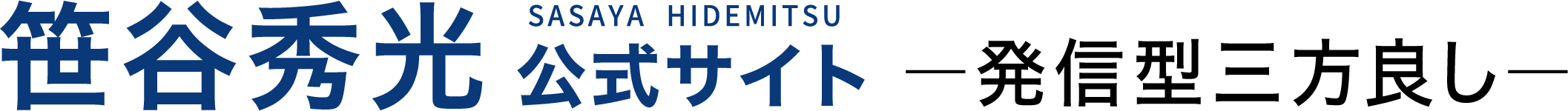2025年3月4日
- 文部科学省サイトより転載です。https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taiken/20250225-ope_dev02-1.pdf
- 教育 > 青少年の健全育成 > 体験活動推進プロジェクト > これまでの実績
審査委員講評:千葉商科大学 客員教授・経営コンサルタント
笹谷 秀光 氏
ポスト SDGs「質の高い教育」としての体験活動表彰
本表彰制度は、設立から 12年目になり2回目から審査委員をして
いますが、その歴史を企業の視点で見ると、まず2010年のISO 26000
(社会的責任の手引き)による「本業を通じた企業の CSR」や 2011
年にマイケル・ポーター等が提唱した「共有価値の創造(CSV)」の
浸透がありました。そして 2015 年には国連での SDGs(持続可能な
開発目標)の策定を受け企業でも積極的に SDGs を経営に取り入れ
ています。さらには投資家を中心に ESG(環境、社会、企業統治)の要請がこれを後押し
しています。これらを総合した「サステナビリティ」(持続可能性)は経営の中核になって
います。
サステナビリティとは、「地球のため、人のため、自分のため、そして未来の子孫のため」
という意味です。重要なのは世代を超えた視点です。活動が、将来の世代、孫子の代から見
ても誇れるものであるかどうか。それを問う価値観が、サステナビリティで、まさに将来世
代の青少年の育成が重要な視点です。
私の専門である SDGs では、目標 4 に関連しますが、単なる教育ではなく「質の高い」
教育(Quality Education)であることが重要です。特にターゲット(具体的目標)「4.7」に「持
続可能な開発のための教育」(ESD:Education for Sustainable Development)が規定され
ています。ESD では実体験でしっかり学ぶ「体験活動」に焦点が当たります。体験型の教
育活動は、社会課題と向き合う学びの場として大きな意義を持っています。
表彰制度におけるもう一つの重要な視点は、企業が本業を活用して戦略的に組み込むこ
とです。企業の活動は ISO 26000 ができる前の「寄付型」や「慈善活動型」から、「事業を
通じた社会課題の解決」に進化してきました。これにより継続性を確保した活動にできます。
また、企業経営では「人的資本経営」が重視されており、本制度は、青少年の教育効果だけ
でなく、従業員のスキルアップやモチベーション向上という側面からも大きな効果を発揮
しています。
達成年度が 2030 である SDGs については、いよいよ年次以降の「ポスト SDGs」の動き
が本格化しました。2024 年 9 月の国連での未来サミットで、2027 年からポスト SDGs に
向けた検討を開始するとされましたので、今から日本提案をまとめていく必要があります。
教育分野も重要な事項ですので、本表彰制度の優良事例がポスト SDGs に向け有力な「玉」
となっていくことが期待されます。今後もこの制度により、青少年が持続可能な未来を見据
えリーダーとして成長する体験の場を企業が提供していくことが、ポスト SDGs 時代の鍵
となります。